
津軽三味線
tsugaru-shamisen

もともとは青森県津軽地方の民謡の伴奏として活躍していた三味線が次第に即興演奏を加えて独立し、1960年代頃に「津軽三味線」と呼ばれるようになったものである。
70年代には高橋竹山などが東京で独演会を行なうようになって注目された。かつては盲人の音楽家が家々をまわって演奏する習慣もあったが、現在は器楽的な独奏曲としてステージで演奏され、若い演奏者も次々と生まれている。独奏が盛んになるにつれて大きな音の出る太棹を使用するようになり、バチでたたきつけるような独特の演奏法も一般化した。現在は他の三味線より一番大型で重い楽器を使用している。
Episode
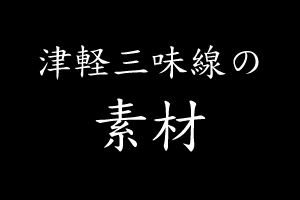
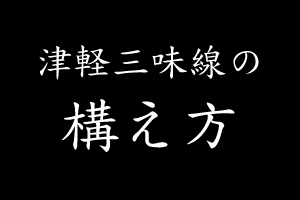
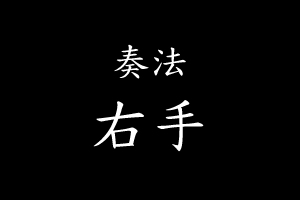
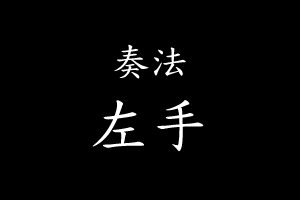
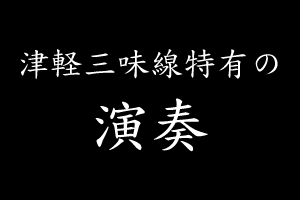
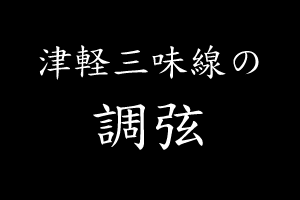
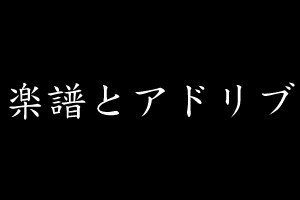
演奏とお話 山中 信人
※ 各エピソードで五線譜が用いられている場合、絶対音の表記で統一しています。
Music Library
津軽塩釜甚句
少しはずんだ軽快なテンポで演奏。津軽塩釜甚句は津軽五大民謡の一つ津軽小原節の元唄で、昭和初期に鹿児島小原節の流行にあやかろうと「塩釜小原節」から「津軽小原節」と曲名が変化した説もある。
津軽よされ節
津軽五大民謡の一つ。三拍子に近いリズムに少しタメを付けて演奏。本来、じょんから節やよされ節などの津軽五大民謡は三味線の前奏後に太鼓が入って唄へと続く。現代では前奏部分が独立し、津軽三味線の独奏として演奏する機会が多くなった。
津軽あいや節
津軽五大民謡の一つ。よされ節に近いリズムで演奏。津軽五大民謡の中でも特殊な音階を用い、唄い手によって長音階(陽旋)、短音階(陰旋)を弾き分ける。また奏者によってリズムのタメ方が異なる。
津軽じょんがら節
津軽五大民謡の中で一番ポピュラーな曲。「旧節」「中節」「新節」「新旧節」と、演奏された時代によって構成やリズムが異なる。特に新節は津軽三味線の独奏として欠かせない一曲。動画では「新節」を演奏。
